令和7年度栃木市民大学受講生を募集します
地域での活動やまちづくりなど、様々な場面で学習した成果を発揮することを目的として“栃木市民大学”を開催いたします。受講生同士の交流・仲間づくりをしながら、一緒に学びませんか?
講義形式で様々な分野について学ぶ「教養コース」と座学やワークショップ等をとおして地域課題の解決に向けて学ぶ「実践コース」を開催します。
教養コース(全13回)
開催時間:14時30分~15時40分
開催場所:とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館)(栃木市旭町12-16)
第1回 細胞の中に薬を届けるシステム開発 ~細胞内ドラックデリバリーシステムについて~
7月8日(火曜日) ※14時20分から開講式を行います。
講師:日本工業大学 基幹工学部 環境生命化学科 教授 佐藤 健一 氏
第2回 データのお話
7月31日(木曜日)
講師:日本工業大学 先進工学部 データサイエンス学科 教授 大宮 望 氏
第3回 ロボット支援手術が変えるこれからの大腸癌治療
8月12日(火曜日)
講師:獨協医科大学 外科学 教授 水島 恒和 氏
第4回 梶井基次郎の文学世界 ~「檸檬」を書いた梶井ってどんな人だろう?~
9月2日(火曜日)
講師:國學院大學栃木短期大学 日本文化学科 日本文学フィールド 講師 岩渕 真未 氏
第5回 情報に振り回されない為の「4つのハテナ」
10月7日(火曜日)
講師:白鷗大学 経営学部 教授 下村 健一 氏
第6回 快適に暮らしたい ~住環境の大切さ~
10月23日(木曜日)
講師:足利大学 工学部 建築・土木分野 建築学コース 教授 室 恵子 氏
第7回 栃木の食文化とSDGs
11月11日(火曜日)
講師:國學院大學栃木短期大学 人間教育学科 生活健康フィールド 准教授 真田智惠子 氏
第8回 eスポーツで楽しく健康に ~デジタルゲームの効果~
12月2日(火曜日)
講師:白鷗大学 教育学部 教授 玉宮 義之 氏
第9回 ストレスを味方にして生きる ~しなやかな心の健康法~
令和8年1月20日(火曜日)
講師:足利大学 看護学部 看護学科 准教授 富山 美佳子 氏
第10回 人の起源をめぐる神話と宗教
令和8年2月3日(火曜日)※講座終了後に閉講式を行います。
講師:國學院大學栃木短期大学 日本文化学科 日本史フィールド 准教授 渡辺瑞穂子 氏
【特別公開講座】(3回)
・認知症市民特別講座 9月15日(月曜日・祝日) 予定
・人権を考える市民の集い2025 12月6日(土曜日)予定
・(仮称)西方城シンポジウム 12月21日(日曜日)予定
※特別公開講座の詳細は後日お知らせします。
受講料
2,000円
※申込期間終了後、6月18日(水曜日)~初回講座(7月8日(火曜日))までの間に、生涯学習課又は各公民館にてお支払いください。(平日)
※栃木市勤労者福祉サービスセンター(ウエルワークとちぎ)の会員及び登録家族の方は、受講料の助成があります。
定員
200名
申込期間
6月1日(日曜日)8時30分~13日(金曜日)17時00分
申込方法
電子申請又は下記の電話番号(平日のみ)でお申し込みください。
ご不明な点は生涯学習課(電話21-2486・2492)にお問い合わせください。
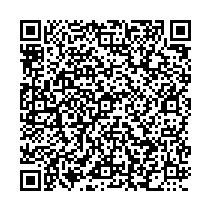
実践コース(全4回)
座学やワークショップ等をとおして、地域活動やまちづくりに参加したり、困っている人をゆるやかに手助けするなど、本市の地域課題の解決に向けて学ぶ講座です。(内容等の詳細は、後日ご案内します。)
第1回 11月 5日(水):「子育てカフェ」ってなに
第2回 11月26日(水):「認知症カフェ」ってどんなところ
第3回 12月10日(水):「子ども食堂」ってどんなところ
第4回 12月24日(水):「ヤングケアラー」の実態は
※会 場 きららの杜とちぎ蔵の街楽習館(市民交流センター)(栃木市入舟町6-8)
※受講料 無料
【申込方法等】
※募集期間 6月2日(月曜日)から6月13日(金曜日)
※申込方法 生涯学習課(電話0282₋21-2486・2492)へお電話ください。(平日のみ)
※実践コースのみ受講することも出来ます。




